![]()
西の大海原と風車がいい・野間岳 [ 591.1m ]
登山口(野間神社)〜第2展望所(30分) [
 この区間の地図
]
この区間の地図
]
野間岳は、宮ノ口から登れば2時間、野間神社から登れば40分もあれば登頂でき、野間岳1山だけでは軽い。幸い笠沙町には見るものは多く、観光とセットするか磯間嶽と2山をセットすれば濃い登山となる。
野間神社駐車場は車道左右に2箇所あり、バックするように神社境内へ向かう。
神社入り口は2箇所あり、右手から登って行く。
左手に鎖が張られた道は神社本殿前に出る。
右手から登ると広場に出、左手に鳥居を見る。
鳥居に額束はなく、文字もない。
石段を登り、鳥居をくぐりさらに石段を登って行と
 本殿前
に出る。
本殿前
に出る。
本殿はコンクリート造りの立派な建物で、派手な朱色で塗られている。
野間神社は、もともと山頂に東西2箇所に建てられていたというが、江戸時代に台風で倒壊し、標高380mのこの地点に移されたのだという。毎年2月20日は、二十日祭りと呼ばれる野間神社例祭が盛大に行われているという。
登山道は、正面に本殿を見て右手の方へ目をやると、登山口らしく数本の立て札が立てられ、第一展望まで270mと案内されている。
そして、足元に「野間岳登山道入口」と書かれた立て札を見て、コンクリート道を登って行く。
辺りは豊富な自然林に囲まれ、鳥の鳴き声が響き渡ってくる。
ゆるやかな傾斜を6〜70mも登って行くと道は左手に分岐、「太郎木場登山口へ」と書かれた立て札が立てられている。
さらに、コンクリート道を5〜60mも登って行くと
 右手へカーブ
し、自然林の中に伸びる。
右手へカーブ
し、自然林の中に伸びる。
7〜80mも行くと左手にカーブして伸び、石段造りになる。
傾斜は少し増し、石段は15段ほど数える。
さらに5〜6段も登ると、傾斜はゆるんでくる。
そして左手へカーブしゆるやかに登って行く。
コンクリート道はさらに続く。
野間岳は大きな山体ではない。それに中腹にある野間神社を登山口にしており、長い時間は要しない。
のんびりと一歩一歩、歩を重ねて行くと、コンクリート道は左手へ鋭角に折れ、道沿いには
 コケむした露岩
が多くなる。
コケむした露岩
が多くなる。
さらに7〜8m登り、左手へすぐ右手へジグザグを切って登って行くと目前が開けてくる。
数メートルも登ると、左手に展望が開け
 西側の大海
が一望できる。
西側の大海
が一望できる。
ここが第一展望所で、擬木のベンチが2 脚置かれている。
登り口には、「展望所まで280m」と書かれた案内板が置かれているが、一部欠損し読み取れないが、これは第二展望所までの距離か、
一息ついて、右手へ擬木の階段を登って行く。
擬木の階段を左右に蛇行しながら登って行く。
さらに左手へカーブし、展望から70段も数えると正面が明るくなる。
右手には、目印の赤いテープを見る。
正面左手には
 白い立て札
が数多く立てられ目を取られてしまう。
白い立て札
が数多く立てられ目を取られてしまう。
ここは、鹿児島県や県内自治体の代表的な樹木が植えつけられ、知覧町のイチョウ・天城町のソテツ等、市町村の名を見る。
自治体の樹木園を見渡し、一息ついてさらにゆるやかに登って行く。
ゆるやかな傾斜にも擬木の階段が付けられているが、その必要は疑問とその思いが脳裏を走る。
左手自治体名に目を向けながら7〜80mも行くと、道は少し傾斜を強め、樹木園を背に右手へカーブして伸びる。
20段も登ると左手へカーブ、さらに擬木の階段を登って行く。
階段は、左右にカーブしながらどこまでも続く。
しかし大きな傾斜ではない。
足元には落ち葉が多く、階段を埋めるように厚く積もっている。
階段が続くと、足はへこたれてしまう。
さらに蛇行しながら60段ほど登ると右手へカーブする。
階段は、すぐ
 左手へ分岐
して伸び、数メートル直進すると左手へカーブする。
左手へ分岐
して伸び、数メートル直進すると左手へカーブする。
左手には真新しい鎖が張られている。
15段も登ると左手へカーブ、さらに階段を登って行く。
20段足らず登ると、さらに右手へカーブし登って行く。
この辺りは、コケむした露岩が多く傾斜も大きい。
さらに、露岩に付けられた階段を17〜8段ほど登って行く。
そして、右手へカーブし露岩の階段を登って行く。
露岩が少なくなるころ、第二展望所に着く。

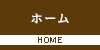
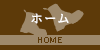
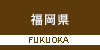
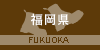
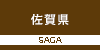
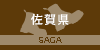
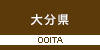


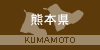
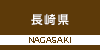
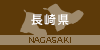
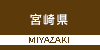
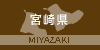
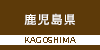
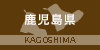
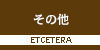







































 登山口案内
登山口案内